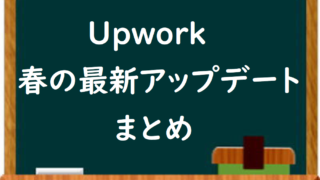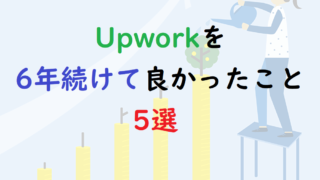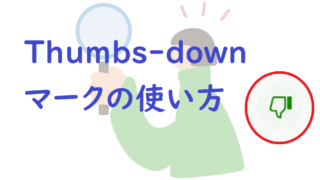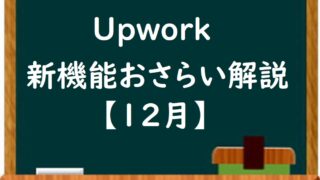【20位~11位】死ぬ前に一度は食べたい!世界のグルメランキング
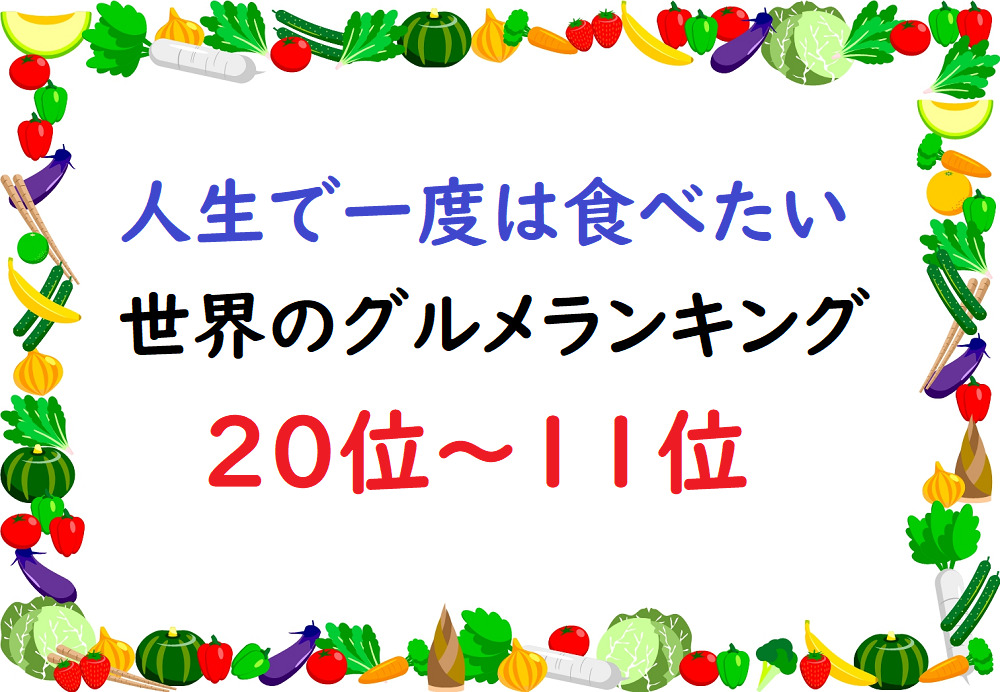
アメリカのニュースサイトのCNNがまとめた「世界おいしいものランキング」に目を通してから旅行プランを立てるのも遅くありません✨
⇒🍅死ぬまでに食べたい世界のグルメランキング50位~41位
⇒🍜人生で一度は食べたい世界のグルメランキング10位~1位
死ぬ前に一度は食べたい!世界のグルメランキング
20位 Pho(フォー/ベトナム)

ベトナム料理と言えば麺料理を始め色々ありますが、まず思い浮かぶのが有名なこちら。米粉から作られたフォーです。
スープと麺というシンプルな組み合わせですが、ここまで世界中で人気の一杯になるまでには、ベトナムの歴史とともに進化を遂げた長い道のりがあったようです。
ベトナムはフランスの植民地だった時代があり、元々牛肉を食べる習慣がありませんでした。しかし、フランス人が牛ステーキなどを食べて余った骨などを利用してフォー・ボー(牛骨スープのフォー)が生まれました。
さらにベトナム戦争の戦時下で中国からの揚げパンと一緒に提供されたり、国内で南北の分断や統一を経て、北のハノイで生まれたフォーが南のホーチミンにも伝わってどんどん美味しく改良されていったのです。
ここから個人的な話です。数年前にラオスのルアンプラバーンから、夜行バスで33時間かけてハノイへ。トイレ休憩は20時間後に1回、荷物は全部車体の外に括り付けてかっ飛ばし、狭い3段ベッドにベトナム人のおじさんが通路にギュウギュウで寝てるおじさん地獄の長距離移動の後でした。
久しぶりに地上に降り立ち、最初に目に入ったその辺の屋台で食べたフォーのスープが死ぬ程おいしくて鼻水が止まりませんでした。個人的にはフォーはトップ10に入るおいしさです。
参考記事:歴ログ -世界史専門ブログ
絶品フォーが食べられるお店ベスト3!👀✨
【ベトナム編】
①牛肉フォーの専門店!フワフワな自家製麺とスープが絶品!Pho VIET NAM
②ベトナムNo.1と呼び声の高いミシュラン有名店、PHO HOA
③ハノイに来たら食べないと後悔するハイレベルのフォー!Pho Thin
【日本編】
①店内は日本在住ベトナム人ばかり…現地の味!リトル・サイゴン・キッチン(東上野)
②予約必須!口コミで絶賛の鶏肉のフォー!ミ・レイ(蒲田)
③自家製生麺がモチモチで美味しいと評判、チョップスティックス(高円寺)
【200人分炊き出しボランティア】フォーの都・ホーチミンへ

19位 Green curry(グリーンカレー/タイ)

スパイスを使った料理は世界中にありますが、やっぱりみんな大好きなカレーには欠かせません。東南アジアの貿易地域として盛んだったタイは、中国やインドからも食文化の影響を受けています。
実はタイカレーは、汁物の一種でインドのような数種類の粉状のスパイスから作られているのではなく、唐辛子やにんにく、レモングラスなど生の食材をすり潰して使っています。さらにココナッツミルクを加えるので、まろやかさも口の中に広がります。
…まろやかなんですが、やはり一緒に加える青唐辛子が本領発揮するため非常に辛く悶絶必死です。
参考記事:loohcs「カレーが国によって違う理由とは?日本と世界のカレーの歴史と特徴」
絶品グリーンカレーが食べられるお店ベスト3!👀✨
【タイ編】
①地元民でいつもいっぱい、ガイドブックにも載る有名店!ガルパプルアック(Kalpapruek)
②ちょい高級だけど店内はオシャレで味は抜群!口コミ1000件以上のナラ(Nara)
③日本人好みのタイ料理!1Fが雑貨屋で女子も嬉しい、ニア・イコール
【日本編】
①タイ料理の価値観が変わる美味しさ!ソウルフードバンコク(池袋)
②この辛さがたまらない…タイの屋台感じる本格レストラン!(浅草)
③自家製のカレーペーストが人気の老舗タイ料理屋、ピッキーヌ(阿佐ヶ谷)
本場のタイカレー料理教室の話

18位 Croissant(クロワッサン/フランス)

ヴィエノワズリー(菓子パン)のトップスター
その起源をさかのぼると、17世紀のオーストリア、ウィーンにたどり着きます。オスマン帝国軍が侵攻してきたとき、ウィーン中のパン屋が警戒を呼びかけて町を救いました。この功績をたたえて、パン職人たちは旧敵オスマン帝国の国旗に描かれていた三日月をモチーフにクロワッサンを作りました。
クロワッサンやヴィエノワズリー(ウィーン風の菓子)の起源は、美味な歴史の始まりでもあります。ウィーン出身のマリー=アントワネット王妃は18世紀、オーストリアのヴィエノワズリーをフランスの宮廷に持ち込みました。これが大好評を博しました。
引用記事:在日フランス大使館
クロワッサンの歴史はストーリーがありますね!やっぱり食べ物の歴史と世界の歴史は繋がっていることが分かります。面白いなあ。
由来が分かったところで、おいしいクロワッサンの見分け方を見つけました。プロのパン職人によるとパン屋が一流かどうかは、クロワッサンの焼き具合で分かるそうです。
まるで、イタリアン料理人の腕がペペロンチーノの乳化の上手さで分かるように…かなり奥の深いパンなのです。
おいしいクロワッサンは…🥐
①焼き上がりが全て統一されている
パンの焼き目を全て同じにするのは至難の業。イースト菌が一番活発になる絶妙なタイミングで、生地の発効時間を見極めて作られています。
②しっかりと芳醇なバターの香りがする
昔は2種類あって、バターの他にもマーガリンで作られていたクロワッサン。成型方法も見た目でどちらを使ったか分かったそうです。
質の良いバターが生地に使われることで、食べる時も芳醇な香りが引き立つおいしいクロワッサンに仕上がります。
③持ち上げると軽い
何層にも繊細に生地を折り込むことで、空気を含み焼き上がりの触感がサクサクになります。また焼成時間も通常のパンと違うため、水分を飛ばしてしっかり焼いているかもポイントです。
あくまで基準です。おいしいかどうかの一番の判断はお任せします。
でも悪いことは言わない、パンとポテトチップスは買うに限る。以下紹介しますので、作るという無駄な抵抗はやめてお店に行くかお取り寄せをおススメします🐟
参考記事:日清製粉グループ パン系女子「クロワッサンラボ」
小さなパン職人*~Petit Boulanger~*「パンのお勉強♪クロワッサン仕込」
絶品クロワッサンが食べられるお店ベスト3!👀✨
【フランス編】
①クロワッサングランプリ受賞!食べないと帰国しちゃダメ!Maison d’Isabelle
②世界中のパン好きが集う!絶品フランボワーズクロワッサン、BO&MIE
③史上最高!パリを代表するクロワッサン、Blé Sucré
【日本編】
①パリと同じ味のクロワッサンを味わう!BOUL’ANGE(日本橋)
②驚愕!エシレバター50%のクロワッサンÉCHIRÉ MAISON DU BEURRE(丸の内)
③日本初上陸!希少バター使用の大きなクロワッサン “Maisonlandemaine”(港区)
17位 Gelato(ジェラート/イタリア)

世界共通の魔法の言葉「甘いものは別腹」、もちろんイタリアでも例外ではありません。イタリアのジェラテリアは国内約4万店あり、日本のカラオケボックスでも全国で6000店程なので、そう考えたらすごい数ですね。
また、ソフトクリームや日本のアイスクリームと違って、空気含有量が少ないため密度が濃い滑らかな口当たりと、果物や素材の味がしっかり味わえるのもジェラートの特徴です。
その昔は、初代ローマ皇帝が奴隷にアルプスの雪を持って来させて、バラの香りや蜜で風味を付けて食べていたという(諸説あり)何ともおシャンティな起源説も知られています。
イタリアのジェラートを食べにローマに行ってみたことがありますが、チョコレートやストロベリーなどの定番からピスタチオ、キャラメル、ヘーゼルナッツなどあまりの種類の多さに迷いまくってしまい、気付いたら私の後ろに長い行列が出来ていたことがあります。
みんな自分の好きな味の組み合わせが決まっているようで、1人3秒の速さで頼んでいました。食べる時はゆっくり味わって、ご飯代わりにする人もいるとか。飯の代わりにはならんとは思うのですが。
参考記事:macaroni「アイスクリームとジェラートの違いを調べてみた」
Delongiを楽しむ「ジェラートは夜中に食べる!?」
絶品ジェラートが食べられるお店ベスト3!👀✨
【イタリア編】
①口コミ数1万件突破!世界最高峰のジェラート、ジョリッティ
②コスパ最高!ローマのお値打ちジェラテリア、オールド・ブリッジ
③お腹いっぱいでも食べられる…70年老舗が誇る濃厚ジェラート!ラ・ロマーナ
【日本編】
①イタリアのジェラートを思い出すこだわり!23時まで開いてるのが嬉しいジェラテリア アクオリーナ(祐天寺)
②濃厚なフルーツ、ピスタチオ味は必須!ジェラテリア マルゲラ(麻布十番)
③ほうじ茶、豆腐、黒ゴマなど和風のフレーバーも人気、伊太利亜のじぇらぁとや(浅草)
16位 Kebab(ケバブ/トルコ)

ケバブ自体はトルコ発祥のようですが、今のピタパンに薄切り肉を削いだスタイルが世界的に有名になったのはドイツに移民したトルコ人が、忙しいドイツ人が手軽に食べられるようにケバブサンドを作って出したところヒットした説が濃厚です。
確かにドイツには労働者不足を補うために、トルコ人が大量に移民となった歴史からトルコ料理屋さんがたくさんあるし、ケバブサンドもボリュームたっぷりでめっちゃ美味しい。
日本でケバブと言えば、周辺に響き渡るトルコの音楽、おやじギャグも使いこなす程流暢な日本語を話す店員、明るいけど強めの客引き、ピタパンに挟まれたたっぷりの肉とキャベツとトマト…ですよね!(私だけかもしれませんが)
トルコ人シェフが語る、日本のケバブサンドが今のスタイルになった理由はいくつかあるようです。
①キャベツたっぷり
日本人はキャベツが好き(焼きそばやトンカツの付け合わせなどいつも食べ物にはキャベツが欠かせない)
②日持ちする
日本では屋台スタイルのドネルケバブが流行っため、トルコでよく使われているレタスだと屋外では傷みやすい。
③安い
レタスに比べたら激安。
ちなみにおいしくするコツは「本場トルコの肉に近づけるため、トルコの音楽を聞かせること」とのこと。なるほど、だから近所のケバブ屋はいつも爆音でトルコ音楽流してるわけか。
参考記事:UROURO TURKEY「本場トルコのケバブにはこんなに種類がある」
ケバブサンド訪問記「日本のケバブには何故キャベツが入っているか」
⇒【自宅であの味を再現】HALAL*スターケバブキット4食(ビーフ2食、ハラールチキン2食)甘口・辛口ソース付き
15位 Ice cream(アイスクリーム/アメリカ)

アメリカのチーズバーガーにかける情熱と同じくらいアイスクリームも日常には欠かせない食べ物です。レーガン大統領は7月の第3日曜日を「国民アイスクリームの日」とするくらいみんな大好き。
アイスクリーム産業化のきっかけは1851年、ボルチモアの牛乳屋ヤコブ・フッセルは余ったクリームの処理に困って、アイスクリームの生産・販売を思い付いたことから始まるようです。
「この余ったクリームどうしよ…そうだ!冷やして撹拌して売ったろ!」→世界初のアイスクリーム工場の始まりです。商品開発はアイデアとひらめきが大切です。
私が「へー」と思ったのは、日本の喫茶店やレストランでお馴染み「パフェ」は、アイスクリームにシロップやフルーツなどを飾り付けて食べてみたら、ヒンヤリ冷たい喉越しや味わいがPerfect(パーフェクト)→「パフェ」になったという説。
次食べるのはいつか分からないけど、パフェを食べる時に誰かに披露したくなるうんちくでした。
アイスクリームの重鎮“Baskin Robins “(サーティーワン・アイスクリーム)が数年前に香りと匂いの専門家を交えて、アイスを選んだフレーバーで性格の傾向が分かるという調査をしていたそうで、時間がある方は下記のリンクからお試しください。
ただ、この会社のアイスは種類が多過ぎるので、「ブルーベリーパンナコッタ」や「メープルスイートポテト」など定番じゃないフレーバーが好きな方の性格は未知数です。
14位 Satay(サテ/インドネシア)

香辛料に漬けた肉を串に刺して焼いて食べるサテも地方によって様々な味付けですが、定番はココナッツミルクを混ぜたピーナッツソースを付けて食べます。これがまた焼き鳥界では新境地の美味さなのです。
昔、インドネシアのジャカルタで有名なサテ屋を探して歩き回りやっと見つけて写真もたくさん撮ったのに、その日の夜行バスでカメラを盗まれて思い出のデータが全て消えてしまい…ショックで3日間引きこもりました。
写真は盗まれても、サテのおいしさは覚えています。ソースは家庭でも作れるし、肉とかなり合うのでおススメです!
13位 海南鶏飯(チキンライス/シンガポール)

丸々茹でた鶏肉とその旨味がしっかり染み込んだスープで炊いたご飯、ホロホロと口の中で崩れる柔らかい鶏肉…甘味のある醤油と唐辛子の利いたタレと絡め食べると最高です。
チキンライスの起源の一つとして知られている話は、中国広東省の南に位置し「中国のハワイ」と呼ばれる海南島で、海南出身の華僑が東南アジアに移民した時に家庭料理として食べられていた料理を故郷の味として伝えたそうです。
なので材料は基本同じで、タレに若干の違いがあるようです。
🐔タイのチキンライス(カオマンガイ)
大豆を発酵させた中国味噌をベースに、しょうゆ、にんにく、しょうが、唐辛子などを加えたタオチオソース
🐔シンガポールチキンライス(海南鶏飯)
チリ、おろし生姜、中国黒醤油の3種類ソース
🐔インドネシアのチキンライス(ナシ・アヤム)
発酵したオキアミを使ったり、ナンプラーを入れたりなど、地域の店によってオリジナルソースを提供している。
🐔マレーシアのチキンライス(ナシ・アヤム/イポーチキン)
生姜と唐辛子をベースとして、さらにニンニクやパクチーなど味に深みを加えたチリソース
現在は、独自に進化したチキンライスが庶民の味として人気ですが、戦時中はバナナの葉にチキンライスを包んで売っていたという話もあります。
鶏肉ってどの国で食べても安定・安心の同じ味です。鶏の親子そろって色んな調理法で調理されていて世界中で愛されていますね。
12位 Kimchi(キムチ/韓国)

ご飯のお供や炒め物のアクセントとして日本でも定番になってきたキムチ。韓国では食べるキムチはまた一味違います。韓国の白菜はシャキッとしていて、長期間発酵された酸味まで濃くておいしいです(気がします)
そしてその違いの1つとなる唐辛子は、日本との交易や豊臣秀吉の朝鮮出兵を通して韓国に入ってきた説が濃厚。
冬前に各家庭では、11月~12月にかけて一冬分のキムチ漬けを行一家総出の一大行事が存在します。その名も「キムジャン」と言い、大きなカメにキムチを詰め、この藁で包んで土の中に埋めます。土の中は温度変化があまりなく、一定の低温が保たれるため、長期保存が可能になりおいしいキムチ作りにはかかせない行事なのです。
さらに、ユネスコの無形文化遺産にも「キムジャン文化」として登録され、天気予報ではキムチ漬けに適した時期を知らせる「キムジャン前線」なるものが発表されるとか。朝鮮半島の気合の違いを感じますね。
参考記事:BASE MAG.「日本と韓国のキムチの違い」
韓国農水産章句品流通公社「キムチの歴史とキムジャン文化」
11位 Lasagna(ラザニア/イタリア)

何たってミートソース作って、ベシャメルソース作って、生地を何層にも重ねて焼き上げるんですから、手間と時間がかかっています。家族のために朝からせっせと準備するおふくろも多いとか。
ラザニアの歴史は古く、古代ローマ時代から食べられていました。豆とチーズと生地を炒めたものでしたが、当時はまだ高級料理だったようです。メキシコのチョコレートやイタリアのジェラートもそうですが、やんごとないお味がするものはまずは貴族から広まっていくので国民の元に届くまでは時間がかかりますね。
元々ラザニアはパスタの1種であり、その材料名が料理名になっています。
参考記事:ひびきにネット「「グラタン」と「ドリア」と「ラザニア」の違いは何?」
パスタ協会公式HP「パスタの歴史」
まとめ
本場の料理を海外まで食べに行きたくなりますね。次回ベスト10🐟